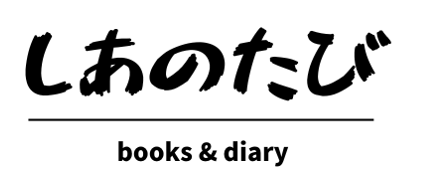前回、初対面での第一印象の大切さを見てきましたが、今回は初対面の具体的な話題を考えてみましょう。メラビアンの法則において、非言語表現が割合として大きいとは言いますが、言語によるコミュニケーションの割合だって、無視していいほど小さいわけではありませんでした。
初対面の話題どーしましょ?
小学校や中学校(もしかすると高校や大学、大人でも)に入学して初対面の人と初めて接するとき「何を話そうか・・・。」などと悩んでる子供たちも少なくないはずです。理屈はさておき、そんな悩める我が子を励ますママの具体的な事例からご覧ください。
でもね、ピーちゃん。話の中身なんてものは、そこそこ仲良くなってからじゃないと伝わらないの。だから、最初の話の中身なんて、な~んでも良いの。初めて会う子と仲良くなるには、まずお互いに自分を知ってもらうしかないよね~。だってそれ無しだと、仲良くなれるかどうか考える材料がないでしょ?だから最初はどんな話しでもいいの。自分の素顔を知ってもらうことが大切ね。
ピーちゃんは犬が好き?猫が好き?そう、ネコちゃん好きなのよね。じゃあ初対面のお友達に、こう尋ねてみて。「ゆーたくんは、犬が好き?猫が好き?」って。そしたらゆーた君がなにか答えるわ。そしたらピーちゃんは、「ふーんそうなの。実は私は猫が好き」と言って、なんでネコちゃん好きなのか色々教えてあげて。そしたらゆーた君もいろいろ教えてくれるに違いないわ。
えーと、すみません。少し作りが雑ですね。こんな説明を聞いてそのまま実行できる子供がいたら天才子役かもしれません。これはいわゆる「質問話法」と「自己開示法」を組み合わせた作例ですが、話題自体は「私は旅が好き」「猫がうらやましい」「わんこは大好きだけど、死なれたとき自分も死にそうになったのでもう無理」「なぜか食器洗いや後片付けが好き」「泣くのがわかっているので、映画館には一人でしかいかない。しかも濡れタオル持参」などなど、テキトーであればあるほど望ましいかもしれません。なんなら、ケン玉で「世界一周」を披露したり、一発芸でスベッてみせても、当初の目的である警戒の解除は果たせるのではないでしょうか?「芸は身を助ける」とはまさにこのことでしょう。
もちろん、この事例はプライベートでのアイディアであって、実際には時と場所、相手に応じた話題選択も重要です。営業の世界なら「キドニタテカケシ衣食住」などの古典的話題事例が有名ですね。キは「気候」ドは「道楽」ニは「ニュース」・・・、あとはググってください。司会の技術としても使われるファシリテーションでは、会議前の「アイスブレーキング」が重要なのだそうです。初対面同士が集まったパーティーなどでは、ペアを組んだ相手の紹介をする「他己紹介」が昔から使われていますが、効果はハズレなく絶大です。そんな他愛もないことしている間に、言い方や声の高さ低さ、拍手や身振りや姿勢、笑顔などが相手に伝わることで、人柄を肌で知ってもらう材料を増やしていくということです。
良好なコミュニケーションのためには、こんなふうに「お互いの言葉が、素直に相手に届きやすい環境を作る」ということが大前提なのですね。少なくとも黙ってちゃ一歩も信頼に近づきませんよね。
期待しちゃダメ&気にしちゃダメ
もちろん、素顔を知ってもらった結果、嫌われるということも(よく)あり。「あざとくない?」「なまいきだわ」「お気楽な人生なのね」なんて陰口たたかれたり・・・。でも、もともと誰からも好かれる方法など存在しません。それに、「人の価値観は尊重すべき」とか言うじゃないですか。だったら、それと同じくらい自分の価値観も尊重されるべきものじゃないでしょうか?
逆に、自分の意見や思いに沿わないからといってすぐに腹を立てて口撃するような人のことを、「身勝手」「ジャイアン」と言いませんか。そして口撃ならまだしもほんとに攻撃するような人は、基本的に人間社会では生き残れません。だって、自分と考えが違う人なんて無限に存在するわけで、その人々すべてにケンカを売っていたら反撃で抹殺されてしまいます。
なのでまとめると、信頼関係のもとに相互理解を目指す「コミュニケーション」では、自分からのアプローチに「見返り」を求めるのはご法度です。それと同じくらい、他人の悪口も100%無視が基本です。しあはこれが苦手ですけど。
場面をもう一度整理しましょう。ここは、初対面の人と仲良くなりたいという思いのある人が、どうしたらそれができるようになるかを考えているところです。一つのアプローチが不評だったとしても、悪口などにカッとしていちいち反応していたら、事態は悪化するだけ。当初の目的を思い出して、悪口は聞き流し、別の手を考えましょう。攻めているのはこちらなのですから。fight!
共通点の発見
でもそうすると、コミュニケーションって、相手の反応の運任せ?
はい、実はその通りなのだそうです。期待してもいけないし、反感も無視しなさいって、先生は言います。それじゃ、お互いすれ違いばかりのように思えます。自分の思いを相手に伝えることは無意味じゃないでしょうか?
先生によると、人はコミュニケーションの中で、「そだね~」「なるほどね~」という部分があったら、自然にその意見を取り入れていくだけなのだと言います。自分に取り入れる話というのは、もともと自分の価値観に沿ったものであることがほとんどかもしれませんが、その「同じ価値観」に触れたとき、ひとは仲間意識を持ってしまう。その共通点を発見したら、そこから話題をそらさず、相手を肯定してみましょう。心が通い合う、というのはそんなところから始まるのではないでしょうか。論理的な会話が成り立つのは、そうした「共感」が生まれたあとのことなのだそうです。
人はみんな、寂しいのだと思います。そんなとき、自分の気持ちや価値観に近い人をみつけ、自分を認めてくれる人が現れたら、誰でも嬉しいのではないでしょうか?しかも「無意識の中」では、それはもうお祭り騒ぎに嬉しいもののようです。人の価値観はそれぞれ、とはいうものの、素直に共通点を発見することがありえます。だって人間だもの(^^♪)
自由意志
ただし!ここで、細心の注意点がひとつだけあります。うわべはどうであれ、人の内心というのは、自分の納得いく話しか受け入れていません。財力や権力で意思を押し通すことはできるかもしれませんが、それは価値観の共有化でも信頼の構築でもありません。人が他人を心から認めるなんて、めったにないことです。この極低確率の現象を、不注意で無効にしては取り返しがつきません。そこで何が必要かというとそれは、
「本人の自由な心理状態」の保障
です。打算や余計な意見を吹き込んだり、脅しで誘導したりした場合、それは本心からの納得ではなくなります。安心して本人の自由に考えてよいことを保障しましょう。
「と、わたしは思うのだけど、ピーちゃんはあくまで自分の思うとおりに決めていいからね~」とでも言いましょうか。ちなみに「と、わたしは思うのだけど」という言い回し、フレーズを「アイ・メッセージ(I message)」と言います。このワンフレーズで「押しつけがましさ」を相当に拭い去ってくれます。自尊心を持った自立したお子さんを育てたいなら、ママの必須フレーズです。
さて、いかがだったでしょう?理論より実例が分かりやすいかと思い、初対面の会話の中に、信頼を築く具体例を描いてみました。
数打ちゃあたるかも
とはいえ信頼を構築するコミュニケーションが本当に低確率なのは誰しも実感のあるところではないでしょうか?なので、実践の心構えとしても「人の思いというのは伝わらなくて当たりまえ、伝わったら超ラッキーぐらいに考えておけ」などと言われます。確かにそれぐらいの覚悟がないと、簡単に心が折れてしまいます。しかし、そんなことでは世界破滅までに間に合わないかもしれません。じゃあ、どうしましょうか?
もう答えははっきりしています。確率が低いなら、数で勝負するしかありません。見返りを求めず、街角に立ち、ただひたすらに自分の思いを表現し続け、物量で勝負する。まるで修行僧のように・・・。あ、しあには無理そう(ぱたり)。
ブログ登場
しかし、行倒れたしあの前に、ついに「いんたーねっと」という援軍が現れます。ちょっと前までなら「自費出版するしかないか~、でもお金ないし~、本を待ってくれているみんな~ごめんよ~」と諦めていたものでした。ところが、もしかしたらタダで、しかも世界を相手に発信できるかもしれない!というのですから、チャレンジする価値あり、となった次第です。
つまり、極低確率の信頼構築コミュニケーションを、ブログ機関銃の射撃速度で補う作戦です。
もちろん、どんなに中身のある内容を書いても、それが読まれなければ意味がないという困難性はあります。でも可能性は生まれました。世界の現状を見れば、戦争を阻止したいというニーズはある。身近なところでは、いじめを無くしたい、パワハラをなくしたい、社員の離職率を下げたい、などのニーズもある。残る課題は解りやすく読みやすい記事原稿の書き溜めと、SEO。
どうせ草稿は書かなければなりませんので、最初からブログを自分のメモ帳代わりに使う。完成したら公開すれば手間いらず。公開しても必要に応じて(恥を知らぬかのように)平然と加筆修正する・・・。SEOはこれから誰かに教えてもらう。よし、これなら、い、いけるかも~。
信頼獲得のコミュニケーションがいかに低確率でも、数打ちゃきっとあたるはず~。少なくとも、打席に立たなければ可能性0ですからね。現代はインターネットがあります。いちいち対面しなくても、コミュニケーションのネットは張れます。ここで、ものすごくお手軽に自己表現が可能で、強力な発信能力があるツールが「ブログ」なのでした。
でも、まあ、ネットも手放しでは喜べない代物であることは知ってます。ネットで傷ついた人もかなりの数になっていると思います。そのことはいずれ取り上げたいと思いますが、それでも、「知る」ことの効率を爆上げしていることは間違いありません。要は使い方次第ということでしょうね。ブログはコメント欄を閉鎖すれば被害なしで自分の思いを機関銃のように発信するツールとしては成立します。
ほとんど費用かかりません。みんなでブログしましょう!