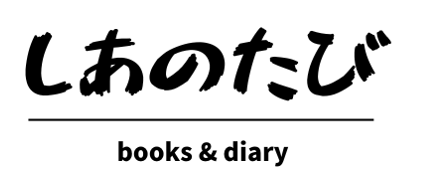いきなり少し寄り道させてください。
ビジネスの世界に限って言えば、強固な組織の構築という課題に対して、信用関係だけで強固な組織を実現しようとするアプローチがあります。それがダイバーシティ・マネジメント(のはず)。今回はその特徴と現状を概観しつつ、実践上では何が課題となっているか、どんな実践能力が必要とされているかをまとめてみたいと思います。
しあが昔これを初めて知った時、「すごいな~そんなやり方もあるんだ~」「でも、実行するとなると、とんでもなく大変だよね~」と思ったことを思い出します。理屈と実践スキル両方が揃わないと物事は前に進みません。
ダイバーシティ・マネジメント誕生の背景
厚生労働省が促進しているダイバーシティ・マネジメントには、いくつかの社会的要請があります。しあは、厚生労働省のことなど興味ないので、詳しくはこちらからご確認ください。推進の必要性としては、1.グローバル化 2.差別撤廃要求 3.多様な価値観がないと社会の多様な要請に応えられない、などなど、皆様が想像される通りの項目しか出てきません。
差別撤廃要求は国内より、外国からの圧力が目立っていませんか?女性の社会進出率が他国に比べて低すぎるとか、LGBTの権利擁護とか・・・。少子高齢化で労働者が減少しているので、外国人に作業労働をしてもらわなければならないとか、日本だけ閉鎖的だとグローバルネットワークからはじき出されるとか・・・。久しぶりにネットを洗ってみましたが、昔とあまり変わらない説明しか見つけられませんでした。
進捗状況
で、ダイバーシティ・マネジメント拡大の実際の推進状況はというと、必死に探さないとみつからないところに、ひっそりと、わかりにく~く、非直接的に掲示されていました。いわく「以前より外国人労働者を雇うようになったか?・・・60%の企業が必要に応じて採用するようになった」「外国人で役員になっている人はどれくらいか?・・・外国人労働者230万人中1%にも満たないが、上場企業を除けば正確には統計が存在しない」「女性管理職は増えているか?・・・ものすごく増えて、15%くらいになった」「女性役員は増えているか?・・・上場企業なら15%くらい。でもそれ以外では統計が存在しない」「ダイバーシティについて社員の意識調査を実施しているか?・・・ほぼ横ばいで、平均で50%くらいが実施」って、これはいったい何の統計でしょう?
「性別国籍の差別なく、趣味嗜好宗教に関係なく個性を尊重し、多様な価値観から新しい価値を生み出す」のがダイバーシティ・マネジメントなら、せかっく日本人にない視点や価値観を持っている外国人の役員がなぜ1%以下なんでしょうか?統計では、「女性役員が多い大企業は利益が出ているので、相関性がある!」と分析してましたが、それって、利益が出てる大企業が外聞をよくするために女性役員を登用してるだけってことありません?それか、もしかしてその女性役員って、性別に関係なく優秀だったりしません?女性が役員になるだけで新しい利益が創造されるというなら、大企業だけでなく他のどんな企業でも自然にどんどん増えていると思うのですが?その形跡はどこにもみつかりません。
こんなしあの疑問に対して、厚生労働省の公式「反論」は、「今までの考え方を抜け出せない」「差別意識がなくなっていない」せいだとの指摘がありました。「念じればどうにかなる」で世の中をどうにかできる人々の言いそうなことですね。それなら問題は、「どうして旧態依然とした考え方から抜け出せないのか」その原因分析と的確な対策が示されるべきだと思うのですが?・・・みつかりませ~ん。
全体としてダイバーシティ・マネジメントは、「世界と取引をするグローバル企業」か「外国人研修生」など、外国人労働者を受け入れている中小企業で役立っているのかもしれませんが、それ以外では目立った広がりを見つけるととができませんでした。もちろん例外はあり、「導入成功事例100社」などが華々しく掲示されていましたが、それは全国492万社のうちの100社の成功事例。逆に言えば、こうした例外事例以外、あまり進んでいないということではないでしょうか?
こうして眺めてみると、つまり、日本経済全体としてみれば、ダイバーシティ・マネジメントに移行する必然性、経済的力学が全く働いていないことが分かります。一部例外企業を除けば、ほとんどの企業にとって、ダイバーシティ・マネジメントは「外国人作業労働者を受け入れるときの環境整備」「みんな仲良くしようね」という合言葉に過ぎないようです。でもね。実は中小企業における外国人作業労働者の皆さんは、「仕事上」で特に差別を受けていたわけでもないんです。作業労働自体に日本人も外国人もあまり差がありません。差別があったとすれば、給与待遇面のお話。これはダイバーシティマネジメントが言うところの「国籍、思想、信条による差別」とはまた別のお話のような気がします。
しあが昔感動したのはそんなダイバーシティ・マネジメントじゃなかったんですけど。
ダイバーシティ・マネジメントの本来の姿
実は、前記事の「信頼構築=無理ゲー」で触れたように、社員同士の信頼構築なんて困難の極みなんです。でも、このダイバーシティ・マネジメントは、信頼関係構築無しに、ショートカットで組織が一致団結できる理論を持っていたのでした。どういうことかというと・・・、そもそも「性別国籍の差別なく、趣味嗜好思想信条宗教に関係なく個性を尊重し」ということは、「個人の人生観や価値観に干渉しない」ということですよね。つまり、人の価値観に触れる「信頼関係構築」にエネルギー割かなくてよい、いえ、割いてはいけないということを意味します。しあは、200㎏の甲冑がいきなりダウンウェアになったかのような喜びを感じたものです。
「性別国籍の差別なく、趣味嗜好思想信条宗教に関係なく個性を尊重し」ということは、極端に表現すれば、「仕事に関係すること以外のお互いの一切の人生観を持ち込まない、干渉しない」「仕事に関してのみ集中する組織をつくる」「仕事を合理的効率的に推進することを目指し」「仕事の成果を上げるために様々な視点からの提案を歓迎し」「理性的に統合し、新たな価値を創造する」ことを意味してしまいます。言ってみれば、「究極の仕事至上主義」ですヨ。
有効な提案であれば、それは誰が提案しても理性的に評価され認められる、ということでもあり、若手社員だろうが女性だろうがLGBTだろうが外国人だろうが宗教的原理主義者だろうが元犯罪者だろうが評価されるということでもあります。実現するならば、確かに思想信条や価値観を脅かされることなく気持ちよく仕事に集中できる、過ごしやすい職場ができるかもしれません。その人がチームメンバーと拮抗する実力がありさえすれば。
ダイバーシティ・マネジメントに求められる能力
でも、これ、しあには無理かも。頭悪いから「仕事の成果を上げるために様々な視点からの提案を歓迎し、理性的に統合する」チームに能力的についていけそうもありません。少なくとも、メンバー全員がこのラインの上でないとチームはうまく機能しません。
仕事中心の組織を作るためには、まずリーダーが相当な力量を備えている必要があります。リーダーはメンバーの力量を的確に評価し、適切な仕事を割り当てなければなりません。できない仕事をやっていて仕事が面白いはずがありませんし、仕事が組織の求心力を持つことはできません。部下の「能力を的確に評価する」ことすらできない上司がいたら、それでチームは崩壊です。さらに、リーダーはアサーションやファシリテーションを理解し、チームの議論を建設的にまとめ上げなければなりませんし、チームの目標設定も適切でなければなりません。人間の信頼を前提としていませんから、横領などができないように、悪意のある行動を100%封殺する二重三重の物理的セキュリティシステムも必要でしょう。
メンバーはメンバーで、チームで新しい価値を創造するというなら、メンバー相互が相手の提案を合理的に理解し、提案する能力を持ち、参画が保障され、気兼ねなく意見を言い合えるチームルールを身に付けていなければなりません。この創造の輪に参画できない人は、チームでの存在意義を失うでしょう。仕事中心の組織を想定してますからね、仕事に力量が無ければ居場所を失います。
創造的な仕事をチームで行うというのは、もともと難しいことなのですが、仕事中心のチームにおいて、実力が欠けているとそれは悲惨な結末を生んでしまいます。ダイバーシティの良さ、つまり多様な価値観や視点をもった人々が集まることのアドバンテージを活かすためには、その多様な価値観を合理的に統合する能力が求められます。単に女性を管理者にしたり、LGBTの人を採用するだけで価値創造が実現できるわけではありません。
それと…、どんなに「人の人生観に干渉しない」と言っても、例えば、極端な話、「イスラムげんりしゅぎ」の社長さんが、「ユダヤきょうのイスラエル人」さんを経理部長として一緒に仕事できるでしょうか?できるとしたらカウンセラーなみの自己覚知(セルフコントロール能力)が必要でしょう。こんな極端なことは起きないにしても、多かれ少なかれ、価値観の相違による不和というものは起こりうるものです。このとき、全員が「そんなの気にしないよ、OK」というレベルの大人で構成される必要ありますよね。これ・・・いけそうですか?「人の人生観に干渉しない」を実現するためには、「人の人生観に干渉しない」を徹底させるため、入ってくるメンバーの価値観に干渉して同意を得なければなりませんし、セルフコントロールの方法も必要に応じて指導できなければなりません。
これ全部取り仕切ってまとめられる実力のある管理者っています?いるんでしょうけど、全国平均で考えて何%?
・・・世の中そんなおいしい話が簡単に転がってるわけないか~~(小梅太夫さんの絶叫><)。
ダイバーシティ・マネジメントの困難性はもう一つあります。それは、実際のところ、結局どっちの組織の生産性が高いか?という現実評価です。困難とコストをくぐりぬけて実現したダイバーシティ・マネジメントであっても、それ以前の旧態依然としたピラミッド組織に比べて生産性が低いともなれば、事件です。この意味では、最初からダイバーシティ・マネジメントが適合する組織と適合しない組織・会社があるのではないでしょうか?そう考えると、統計も正直な結果を報告をしているのかもしれません。
みなさんの会社や組織ではどうでしょう。しあの知る限り、google japanなどが悪戦苦闘してなお途上というお話を遠い昔に聞いたことがあります。その後を知っている人いたら教えてください。
あって損はない、知能
でも、しあは「ダイバーシティ・マネジメント」の考え方を全否定ではないのです。実現に必要な能力を調べて唖然としてはいますが、それらの能力はダイバーシティ・マネジメントに限らず持っていて損はないどころか、持てるなら持ちたい能力だったりします。こうした能力の全体像を言い表すのは容易ではありませんが、人事考課の業界では「精神的習熟能力」という言葉があります。ひろゆきさんが口癖のように言う「頭がいい人」と案外似ているかもしれません。
なんとなくですが、世界平和実現のための方向性や理論の議論も大事かもしれませんが、最後には人類の「知能」がモノを言いそうな気がしています。どの道を辿ろうと、人類が脱皮するには、それに応じた「知能」の底上げが必要かもしれません。しあがひろゆきさんを嫌いになれないのはこのあたりに原因があるのかもしれません。(とはいえ、好きではないですよ。ひろゆきさん、諸悪を「頭の悪い人」のせいにして、分断を増長させてますもの。)
それにしても、この予感が当たるなら、この「知能」について、真正面から考えなければならないときが来るのかもしれません。評論家ではなく、教育者とか指導者とか実践者の立場で取り組んで研究している方を大急ぎで探し始めるとしましょう。
今回は少し寄り道で「信頼」を度外視して組織や社会を結び付ける「ドライ」なダイバーシティ・マネジメントについて触れてみました。そういうルートもあるんだ、程度に留め置いていただければ幸いです。ではまた次の記事でお会いしましょう。御機嫌ようお過ごしくださいませ。