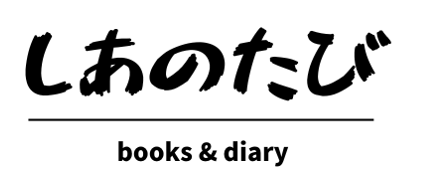「0100.教育の基本の基本」で触れたように、ここでこれまでの「教育」の流れを確認しておこうと思います。これも、「やさしい教育原理」からしあがテキトーに抜粋しました。どこも「やさしく」なんかない本でしたけど、手元に一冊置いておいて損はない「役立つ」本だと思います。ただですね・・・、最初にゴメンナサイしておきます。カンの良い方はお気づきかもしれません。今回のテーマ、これって4団体世界統一王座決定戦なみに「ビッグタイトル」です。どんなに短くまとめたとしても「長文必至」なのです。むしろ今回は、しあ自身の理解と忘備録として記載しました。なので、よっぽど興味があれば別ですが、まあ、「みなさまは読まなくていいんじゃないかしら?」と思わないでもありません。ここはやはり、書籍購入が正解だと思いますよ。
さて、気を取り直して始めましょう。純粋に教育理論を学びそれを理解し改善する取り組みも大事。でも教育って、現実の政策です。今なぜこんな教育政策が存在するのか、その理由を知ることも大切ではないでしょうか。もし現代の教育に問題があるとしたら、その成り立ちを知らずして改善することはできないと思うのです。教育政策の歴史を調べることで、現在の教育がどんな位置にあるのか?教育のこれからの課題は何か?などが浮かび上がるとイイナ、と思ったりします。
でもこれって、多分に思想信条によって意見の分かれる領域であったりもします。「現実重視なのか未来重視なのか」「ユダヤ教徒の教育観なのかイスラム教徒の教育観なのか」などなど、立場によって意見が分かれるところだろうと思います。何が正解かなど実は存在しないのかもしれません。ただ、わたしたちは生き方を自分で選んでいかなければなりません。そのためにも、今までの事実をできるだけたくさん知って、その上で自分の意思を以て判断していくしかないのだと思います。というわけで、事実としての教育の歴史を追いかけてみましょう。
もっとも、これから記すのは現段階シロートのしあが読みかじった本の知識に過ぎません。いずれまた、新しい見識や反対の史実を見つけるかもしれませんが、そのときはまた追記していくことにしましょう。みなさまもおかしなところに気が付きましたら遠慮なくご指摘ください。「本当のことがわかるまでみだりにモノを言ってはならない」などと言っていたら、人は一生沈黙を守るしかないのですから。
教育の起源
えーと、「0100.教育の基本の基本」でも触れたとおり、「教育」自体は世代交代の第3の方法でもあり、進化の過程でヒトが獲得してきた特質でもありました。どうやってその特質を得たかについては考古学や進化生物学などのお宿で扱うことにしましょう。とにかく、ヒトの親は生きていくことに必要なことを生後長い時間をかけて教えながら子供を育てるのでした。でもそれが社会的教育システムとして定着するには相当な時間がかかってしまいました。人類750万年の歴史の中で国家が教育を司るようになったのは、世界四大文明以降のことでしょう。古く見積もってもざっくり1万年前以降のこととしか考えられません。判っているところだけ言えば、紀元前3千年紀メソポタミア・シュメールでは「エドゥブバ」(粘土板の家)という施設があったらしく、役人になるための読み書きや計算を教えていたそうです。「学校」という形が記録されているのはギリシア時代のこと。これは農耕革命による余剰生産物の管理のために、支配者層のための教育が必要になったからです。もちろん学校と言っても公教育ではなく、一部の支配階層が必要に応じて立ち上げたもので、一般庶民に学校など縁のないお話でした。とと、ここから始めると歴史書になってしまうので、また別の記事にしたいと思います。ここは産業革命前後に跳びたいと思います。
産業革命と学校
ヨーロッパでも日本でも、16~17世紀に社会の生産構造が変わってきます。大魔導士アイザック・ニュートン(1642-1727)が1665年に万有引力に気付いてからというもの、人類は転げ落ちるように生産力偏重の道を走り始めます。そうです、みんなお金に目が眩んでしまったのです。日本でも、戦国時代が終わり江戸時代に入ると様々な生産技術の向上が見られます。まず、社会が安定したことによって物流商業が発達し、幕府による新田開発促進などに伴い農機具などの発明工夫が進みます。詳しいことは学校の教科書をご確認ください。平賀源内(1728-1780)さん辺りを調べると面白いですよね。こんな中で天保年間(1830代)以降「寺子屋」が急増したりします。
そして迎えた産業革命。高い生産性が余剰を生み出し、公教育を実現する余裕を生み出します。その返す刀で、公教育は労働者として必要な能力養成を行うと同時に道徳教育を織り込みつつ資本主義支配を支える民衆支配装置として機能します。まあ、そうした力学がなければ、公教育なんて生まれなかったんですから、仕方ないですね。資本主義に後押しされる公教育はどんどん広がっていきます。
公教育は根本的には資本主義の支配装置であったとはいえ、先行して生まれていた啓蒙思想によって、時々は人権回復の方向性を見せたりもしました(「啓蒙思想」については別記事で扱いますね)。宗教的弾圧や産業革命による過酷な生活にあえぐ子供たちを救済すべく平等で普遍的な知識教育を願った人々も現れたりしたのです。近代人権思想の発展や市民革命を通じて公教育の見直しが議論されたりもしたのです。さらに公教育によって「知」が社会全般に爆発的にひろがる役目を果たしたのは事実でしょう。ただ、資本主義が帝国主義(国家間競争・植民地争奪戦)へと脱皮する中、戦争などが始まるとそんなヒューマニズムは、あっという間に吹き飛ばされてしまいます。これまでのところ、教育の理想論は数多く存在しましたが、産業や経済に変事が起こると、それを主導管理する「国家」によってジューリンされてきたというのが公教育でした。
それでも時々現れる人間性回復を目指した教育理論、例えばデューイらの子供の自主性を重視した教育法が日の目を浴びることもあるのですが、それもあくまで「先進国において、新技術開発を担う人材育成に効果的だった」から採用された、とも考えられます。昨今の先端技術の開発には、暗記中心の受動的学習では役にたたないからです。とは言いながら、デューイの主体性教育が人間性回復への足掛かりになっていることもまた事実。影を含みながら光を放つ、教育ってそんなところがあるのかもしれません。「0100.教育の基本基本」で取り上げた、「個人と社会の循環関係」の仲立ちとして存在する「教育」の役割と言うか位置づけと言うか特性と言うか、なんだか急に生々しく考えさせられます。
公教育としての学校
ヨーロッパで公教育が国家的な施策として始まったのはフランスで、フランス革命(1789~)後、コンドルセが義務教育を国会で提起(1791)したあたりが始まりと言われています。ジロンド派であったため失脚しましたが、後々フランスの教育無償化につながっていきます。日本の学制はフランスの学制を模倣して始まっています。世界の植民地主義に危機感をいだいた日本政府は富国強兵を急ぐべく、明治に改元(1868)して早々の1872(明治5年8月2日)には学制を公布しました。
ざっくばらんな史実確認でごめんなさい。大事なことは、こんな風に社会の生産体制が変わると、そこに求められる人材も変わらざるを得ないし、そんな人材を育てるための教育も変わらざるを得ないということ。公教育とは、どこまで行っても、社会の生産を担う人材の育成を目的とするものです。もしそうでないなら、つまり社会の役にまったく立たないなら、社会が経費を投じて公教育を推進する動機が生じません。必然的に、求められる「教育」も時代に左右されてきたということです。
学生のみなさん、この点に気づいてない人、いませんでしたか?しあは学生の頃「勉強やピアノ練習はあくまで自分個人のもの。自分が好きで勉強してる。周りの人なんかと全く関係ない。」と思っていました。ちょっとはずかしいです。それと、教育の歴史を知らないと、今自分が受けてきた教育だけが「教育」だと思いがちです。歴史的事実としては、国家による公教育が始まって以降は、国家の都合で教育の内容が左右されてきたということを認めなければなりません。それは、あえて偏った表現を使えば、「為政者による洗脳」であったりもしたのです。怖いですね。でも、戦前の日本や現代でも周りの国を見渡すと、思い当たることはないでしょうか?そうです。歴史上そんなことはありふれた話なんです。
農村と都市の教育ニーズの違い
公教育の中身が「為政者の洗脳」である割合は、時代や国・地域によって違いがあるでしょう。独裁国家と民主主義国家とではその割合は違うでしょう。でも、教育の内容を決めるのは為政者や統治機構だけではありません。民主主義国家でも、市民が何を求めているかによっては、そこそこ歪んだ教育が行われたりします。
例えば、「高学歴であればよい会社に入れて安定して高収入が得られる。」という世情があると、市民はそれにノッカルために子供に受験対策の塾通いを強制したりします。強い親心なんですけどね。日本のように景気が悪くなると一層その傾向が強まるようです。もし勝ち組に残れなかったら、滑り台を下るように社会の敗者に転げ落ちる危険性があるからです。韓国も相当ひどいみたいですけどね。そこに来て、資本主義の申し子である核家族時代のおかげで近所付き合いはほぼ壊滅。「周りはみんな敵。」とは言い過ぎかもしれませんが、村落共同体とは違って、人々はむりに近所付き合いしなくても生きていける環境を生み出したのが資本主義です。中には家に閉じこもって、我が子の現状や特性を把握もしないで我流の無茶な教育を強いたりする。無差別殺人の第一段階到達です。
一方で、農村で生きるだけなら、高学歴どころか、たぶん学校自体不要です。農業に必要な知識・技能は、小さいころから作業を見たり実際に手伝うことでほとんど修得可能です。(もちろん、現在の農業も科学技術の進歩や経済管理を取り入れてますので基礎学力は必要ですが、農協などの指導者についていくだけなら体一つでなんとかなります。)また、生産の特性上、地域の協力も必須です。水路だって共用ですし、繁忙期には相互に協力しないと種苗や収穫に遅れが出たりします。そうした共同体の中で人々は子供たちを「村のこども」として育ててきました。村内では、誰がどの家の子で、どんな性格しているか、どんな能力持ってるか、何が好きなのかなどを相互に知っていました。だから、相手がどんな気持ちでいるのかなど容易に理解想像できる関係の中で暮らしており、時には損得を超えた人間関係もありえたのです。そしてこれが人類の歴史のほとんどを占める生活スタイルなのでした。
子供の生存率が低かった古代からずっと、子供は集落の存亡を左右する最重要存在として、あの手この手で育て上げられてきました。「神のうち」とか「氏子入り」とか「七五三」などの習わしにどんな意味があるか調べてみると、その切実さにジ~ンときてしまいます。さらに子供の異年齢自治集団=「子供組」が組織され、正月の「火祭り」や夏の「虫送り」などの行事の主催者として活動が促されていました。そんな関係の中で、鬼ごっこやかくれんぼ、かごめかごめなどの子供文化も継承されてきました。成人式以降は、娘組、若者組などが組織され、合宿所まで用意されたりしました。仕掛けは他にもびっくりするほどたくさんありますが、こんなふうに農村共同体でも、相当な人間形成システムを保有していたのでした。人類の歴史からすれば、そっちの方が大半を占めるわけです。なので、現代の受験競争がなんか不自然で息苦しいと感じるのはむしろ当然ではないでしょうか?文明は発達しても、体は数100万年前から変わってないのが人間です。少なくとも、現生人類が主戦場として暮らしていたのは「狩猟・採集生活」の世界であり、多くても150人前後(これを「ダンバー数」と言う)の村落共同体でした。ホモ属4万年の歴史のうち、人々が農村を離れて都市で生活し始めるようになったのは、日本においては明治以降、つまりたかだか150年前のおはなし。本格化したのは第二次世界大戦後の1950年代以降のことです。まだたったの80年。そんな短期間に、体や脳がついてきてるわけがありません。(あ、この話はまた別記事にしますね。)
このように、地域や生産システムの違いによって必要な教育内容も違いますし、現実の教育の在り様も地域によってまだら模様なのだと思います。ただ、資本主義によって推進された産業革命以後都市部の「教育」は、「科学的知識」「技術の充実」「生産効率をあげるマネジメント」はあるものの、人間形成という領域では村落共同体が担っていた大事な部分をゴッソリ投げ捨てているように見えます。みなさんの周囲ではどうでしょう?
戦前の日本の教育
ここでは、明治5年の「学制」以降、日本の教育制度史の転変をまとめておこうと思いますが、詳しいことは、あとで気が向いたら書き足すことにします。だって、疲れてしまったのですもの。ものすごくおおざっぱに書き残すとしたら、先進諸国の植民地政策=侵略戦争に対抗するため、急速な富国強兵の必要に迫られた明治政府は、欧米文明を吸収し産業革命を実現するために公教育を急いだのでした。個人の力量、国民の力量が高まれば必然的に国家の力も強まる、と思ったらしいのです。福沢諭吉先生も「一身独立して一国独立する」と言っていました。なので、最初の頃は素朴に公教育を推進する政策でした。
ところがこのとき、欧米の近代人権思想も輸入されます。これが自由民権運動の土台となります。そこから中央集権を目指す政府と自由民権派が目指す教育の自由とのねじりあいが繰り返されます。「個人の自立を図ることによって国家の独立を達成する」という教育理念と「国家に従属する個人を形成する」という相反する教育理念の間で、教育政策は何度も揺れ動きました。その結果、明治23(1890)年になって教育勅語で「臣民」像が示され、道徳教育が強調され、中央主権側の勝ちとなるわけです。
でも、この中央集権的な教育理念も、思わぬところから動揺を始めたりします。それは大正時代、都市で暮らすようになった「新中間層」市民からの要請です。都市で暮らすようになった市民にとって、資本主義社会は競争社会でもあり、その競争に勝ち抜くためには更に高度な教育、子供の能力を伸長させるような教育への欲求が膨れあがってきたのです。道徳教育を中心とした天皇崇拝、画一的で受動的に知識を詰め込む一斉授業中心の学校教育に対して、「実力養成ができていない」と批判が高まったのでした。このころ欧米でも「子供を教育の中心に据え」「子供の発達の必要性に応じた教育の創造」が始まっており、日本でも1910~20年ころにかけて実際にいくつもの私立学校が創設されたりしました。結局、資本主義は新たな教育改革を求める起爆剤ともなったのです。
ところがですよ、二転三転とはこのこと。当時の資本主義の労働者搾取は極悪非道なもので、その反発として社会主義思想を生み出していました。これが大正デモクラシー運動を拡大し、小作争議や労働争議も頻発します。これに驚いた政府は、思いっきり教育の統制を強化します。時は1914(大正3)第一次世界大戦、1917(大正6)ロシア革命、1923(大正12)関東大震災。社会は緊張のど真ん中にありました。こんな緊張状態の中で暮らしていたら、もしかしたらしあでも中央集権を支持するかもしれません。とどめは1929(昭和4)世界大恐慌。子供たちは学校に来ないどころか、身売りが頻発しました。
さて、この混乱状態の中、日本の各地では子供たちを助けるため「生きていく力となる学力」をつける教育の創造を目指す実践研究が興ります。「郷土教育運動」「生活綴り方運動」「生活教育運動」・・・。逆境にあって、よくもこんなに頑張ったものだと思います。ここだけは頭の片隅に残していい歴史的事実だと思います。
さて、あとは第二次世界大戦。もうよくご存じですよね。国家総動員法だの、学徒動員だの、教育は崩壊します。
戦後の日本の教育
さーて、敗戦後、日本の公教育も民主化されたでしょうか?
1.GHQによる教育改革
戦後日本の教育制度を方向づけたのはGHQの占領政策でした。1946.11日本国憲法、1947.3教育基本法が制定されます。憲法第26条においては、国民はその能力の発達の必要性に応ずる「教育を受ける権利」をもつこと、子供たちに「普通教育を受けさせる義務」を負っていることが規定されています。教育基本法には、憲法の理想とする国家、社会の担い手、主権者になるにふさわしい人間を育成することを目指し、「個人の人格の完成」とか「平和的国家および社会の形成者としての諸資質」の育成こそが教育の目的であることが記されていました。戦前の教育目的(臣民化)を転換し、一人一人の子供の持つ多様な可能性に寄り添いながらその能力を発達させ、自己の人格を完成させていくことを教育の目的としたのでした。
具体的な教育行政の変革としては、戦前の政府(内務省)主導の教育行政を転換し、1948年教育委員会法が制定されました。各地域に一般行政から独立した「公選制」の教育委員会を設置し、地域の教育行政について大幅な権限を与えました。
2.戦後新教育運動
GHQの方針に従い、新生日本政府文部省も学習指導要領の試案を作成します。そこには「今度はむしろ下の方からみんなの力でいろいろと作り上げていく」などと方針が示されており、全国各地で「その地域や学校に即した教育計画を教師自身の手で作っていこう」という機運が巻き起こります。これを「戦後新教育運動」と言います。地域社会の課題を探求し、その課題を解決しうる力をつけるためのカリキュラム作りが進められ、そのカリキュラムに基づいた問題解決学習の実践が展開されたのでした。戦後の混乱期から教育の立て直しに立ち向かった教師たちの姿は、大田尭先生の「かすかな光へと歩む生きることと学ぶこと」に詳しいです。元都留文科大学の学長さんですね。この本は『かすかな光へ』として映画化もされています。新しい日本の教育を想像しようと意欲に満ちた実践研究が様々に取り組まれ、教師や研究者による民間の自主的な教育研究組織が数多く編成されたのでした。
3.東西対立と戦後教育の変質
ところが、1950年代になると戦後新教育運動も陰りをみせることになります。1949年中華人民共和国成立、1950年朝鮮戦争が勃発します。占領政策は「徹底した民主化」から「共産主義の防波堤構築」へと急転していくのです。1951年サンフランシスコ講和条約、日米安全保障条約が結ばれ、日本は自由主義陣営の一員として独り立ちが求められます。ここで占領政策は明らかに転換され、教育に対する国の権限の強化や教育行政の中央集権化が促進されることになります。
1953年学校教育法の改正では教科書検定の権限者が文部大臣に戻されます。1956年教育委員会法も改正され、教育委員会の「公選制」が廃止され地方自治体の首長による「任命制」に変わり、文部省の指揮監督下に置かれるようになります。1958年には学習指導要領が改正され、それまで「試案」だった学習指導要領が「公式発表」となって拘束力をもつようになります。「下の方からみんなの力で」と言っていたものが、中央集権化し、科学教育重視、系統学習を重視した教育カリキュラムとなり、道徳教育が導入されました。
これは、アメリカ政府日本政府の思惑だけでなく、日本の民間経済界からの要請も色濃く反映されたものでした。1950年朝鮮戦争による特需景気が巻き起こり本格的な戦後復興が始まります。この経済発展に適した人材育成が求められたのです。そんな中、1954年教育の政治的中立性に関する教育2法が制定され、教育公務員(特に公立学校の教員)の政治的行為を制限し、義務教育段階の学校において教職員が児童・生徒に特定の政党を支持・反対させるような教育を行うことを禁止します。また1957年教職員の勤務評定が実施されます。この揺り戻しの中で文部省と日教組の対立が激化したことは有名です。国の都合か、教育の自由か。
4.高度経済成長と教育
これは経済政策のお話ですが、1963年経済審議会が「経済発展における人的能力開発の課題と対策」として一つの答申を出します。いわく「経済発展を支える労働力として人的能力の発見と要請を効率的に進めるための学校教育の再編」が提起されています。具体的には、中等教育段階で能力選別し、その能力差に応じた教育システムを作ることを求めたのです。全国学力テストの真の目的は、優れた人材の早期発見だともいわれていました。これに応じるように1966年中央教育審議会では「後期中等教育の拡充整備」として、適性能力に応じた多様な学科の設置、高度な素質を持つ者に対する特別教育、高校教育のより一層の多様化などが提言されています。
つまり1960年代においては、「個々の子供が持つ多様な能力を発達させ、自己の人格を形成し、実現するために必要な教育を保障する」といった戦後直後の教育方針から、「国家社会の発展に必要な人材を配分供給するという観点から、子供の能力を測定し、その程度に応じた教育を受けさせるシステムとして学校教育を機能させよう」という教育方針に転換されたのでした。1964年10月10日東京オリンピックに象徴されるように、高度経済成長に誰もが狂奔した時代です。勝ち組と負け組が鮮明になる時代でした。1960年の高校進学率57.7%が1970年には82.2%まで上がっていきます。この間、高校の序列化、大学間格差、激しい受験戦争、学習塾増大、偏差値重視、テスト漬け教育が広がります。
この時代こそ、2008/6/8秋葉原無差別殺人事件を引き起こした加藤 智大(25歳)の母親が教育を受けていた時代です。「やさしい教育原理」によれば、「産業の構造変化を基礎とした高度経済成長は、村落共同体の決定的な解体をもたらし、社会・文化構造のみならず、衣食住の基底部分を含めて、かつてないほどの急激変化をもたらしました。大正期に都市新中間層に生まれた少産少死の「教育家族」文化は、都市部のみならず農村部にも一般化し、子供の教育に関する、とりわけ学校教育への期待は、国民的規模で高まっていきました。」と語ります。これが、事件の背景要因の一つですよね。
5.詰め込み教育による大災害
こんな調子で受験競争が繰り返された果てに、その教育の質が問題となる状況が現れ始めるのが1970年代後半のことでした。このころ現れた教育現場の問題を表すキーワードが、「ツッパリ」「落ちこぼれ」「校内暴力」「学級崩壊」です。学校外でも「暴走族」が大量発生していました。というか、「廊下をバイクが走っているのが日常だよ」という中学校があると聞いたことがあります。アンケートで「できれば学校に行きたくない」と答えた教師は3割に達していたと言います。突出したところでは、7割を超えていたそうです。教室が戦場化し、教師が暴力や無力感にさらされるという異常事態。「金八先生」が大ヒットした背景です。そこには「管理教育」とかそれに付随した「統制的道徳教育」がありました。「道徳教育」についてもまた、別記事で取り上げることとします。
まあ、被害甚大の教育現場が1970~80年代と続きましたが、要点をまとめると、個々の子供のその時点での発達欲求と関係ない知識は消化されないし、詰め込んだら消化する時間もなかったというだけのことでしょう。あげくに、学力格差が社会格差を意味するとあっては、負け組はグレるしかありません。それに対処しようとした道徳教育も、本人が「なるほど」と自己判断し選択したものでなければ内実化しないというだけのこと。社会秩序の維持を重視して、上から結論を押し付ける思想統制がごとき道徳教育では通用しなかったということでしょう。学級崩壊なんて、しあにはごく自然な現象だったように思えます。しあにとって大事なことは「危ないことに近寄らないこと」でした。知識や道徳は、自分で扱い方を考え、実際に使ってみて、消化して初めて使い物になる学力や人生観になるという、ごく当たり前のことが理解されていなかった時代だったと思うのです。もしくは、理解している先生がいたとしても、生徒個々によって異なる発達課題に対して、手が回らなかったのだと思うのです。基本、一斉授業ですからね。
そのうち、1991年3月バブルが崩壊していて、「フリーター」や「ニート」が現れます。「不登校」や「引きこもり」も本格的に増加しました。吹き荒れていた校内暴力は体育会系暴力教師の活躍によって鎮静化しつつありましたが、代わって陰湿な「いじめ」が広がり始めます。ひきこもりの宮崎勤による東京・埼玉連続幼女誘拐殺人事件が起こったのが1988年、大阪愛知岐阜連続リンチ殺人事件が1994年、酒鬼薔薇聖斗を名乗る中3生徒による神戸連続児童殺傷事件が1997年です。「いじめ防止対策推進法」の契機となった大津いじめ自殺事件が2011年のこと。学校や世の中を安全なところと信じてはいけない、と強く思ったことを覚えています。
と、忘れないように書いておきます。しあは、政府や学校側はこの大災害を最初から予想していたのではないかと疑っています。だって、一つの基準(受験)で選抜を強化すれば必ず敗者が生まれるのは、やる前から判っていることだからです。でも、どうして?その答えに対するしあの仮説はひとつです。高度経済成長をリードする優秀人材をふるいにかけて育てることこそが第一目標であり、こうした大災害は最初から仕方ないと考えていたのではないでしょうか?早い話、日本の戦後教育は経済成長第一主義に追従してきただけのことのようです。もちろん「それを望んだのは誰だったのか?」ということについて、わたしたち一般国民に責任が全くなかったとは思わないのですが。
6.ゆとり教育の登場
大災害を目の前にして、さすがに「まずい」と思ったのか、1980(昭和55)年「ゆとり教育」が指導要領に盛り込まれます。しかしどうしたものか、それが動き出すのが1992(平成4)年と、12年もかかっています。経済優先、優秀人材輩出を優先する「学力維持向上派」の反対が根強かったとも言います。ようやく具体化したものとして1998年の学習指導要領で創設された「総合的な学習の時間」が象徴的。2000(平成12)年に小学校3年生から導入され、2002(平成14)年高校まで実施されるようになりました。内容としては、社会の変化に対応する力の養成を目的として、子供たちが自ら課題を見つけて学ぶ力を育てる時間とされています。なんだか前に見た「2.戦後新教育運動」の流れを引き継ぐものを感じます。このころ、実社会でも「職場QCサークル活動」が盛んだったことが思い出されます。具体的な教育事例や活動事例をここで広げる余裕はありませんので、興味ある方はリンクで確認してください。また、次項で触れる「脱ゆとり教育」政策の中にあっても、「総合的な学習の時間」は時間短縮されつつも継続しています。
そんなこんなで2002(平成14)年、学校が完全週5日制に移行して、物理的時間によって学校での「ゆとり教育」が具体化します。しあみたいな勉強嫌いの子にとっては、幸せな時代がやってきました。でも、周りの真面目な子をみると、本当にみんな塾通いで、遊ぶ時間なんて前より少なくなっていたように見えました。しあは塾通いしたことないので「自分だけこんなに遊んでいていいのかな?」と不安を覚えた記憶があります。こんな不安な状況で、ノホホンと遊んでいたしあは、むしろ特殊だったかもしれません。
そうこうしているうちに、ちょっとショックな情報がもたらされます。OECDでは2000年から生徒の学習到達度調査をしていました。PISAと言い、現在も続いています。15歳(高校1年生)を対象として知識や技能を実生活で活用する力を調べています。そのPISAの日本の成績順位がどんどん下がっていったのです。

「テスト成績なんて気にすることない」と、しあは思うのですが、文部省はこれを気にしたようです。「これは、ゆとり教育のせいに違いない!」と考えた文部省は、2011年「脱ゆとり教育」へ方針を転換しました。いわく、「ゆとり教育は競争意識を希薄化させ、学習意欲を削いだ」とかなんとか。あまり説得力のない理由で方針が決まったように見えました。
なぜかというと、どの項目でも上位を走っているフィンランドは、1990年以降「ゆとり教育」「総合学習」を徹底的に推進しているからです。学力低下の原因をゆとり教育に求めるのは無理があります。学力低下には他に原因があるに違いありません。これを読み解くためには、そもそも「学力とは何か?」について基礎的理解が必要になると思うので、前項でもお約束した通り別記事で「学力」を取り上げ、それから考えることにしたいと思います。
7.今日の教育制度
「ゆとり教育」から2025年現在までの教育政策を確認して、記事を締めましょう。
国際学力調査での順位低下に驚いた日本は、「脱ゆとり教育」に舵をきります。2008(平成20)年の学習指導要領の改訂で授業時間が増加し、小学校では2011年度から、中学校は2012年、高校は2013年から完全実施されました。「総合的な学習の時間」の目的である「生きる力」の理念は維持しつつも、内容的には「基礎的・基本的な知識技能を習得する」方向へ転換したと言います。具体的には、「授業時間の増加」、「思考力・判断力・表現力の育成(知識の詰め込みではなく活用力を重視)」、「学習意欲・習慣の確立(主体的に学ぶ姿勢を育てる)」、「道徳教育の充実(心の教育)」、「伝統・文化の尊重(縄文時代や文化遺産など日本の歴史や文化への理解を深める内容が追加)」などがあげられています。具体的には、理数系の授業時間が増えプログラミング教育も導入されました。小学校でも「理科」が復活し、観察・実験を重視した内容になりました。国語の授業以外でも、話す・聞く・書く・読む活動を重視するようになり、社会科に「縄文」や「文化遺産」の学習が明記されました。道徳では「心のノート」などが導入され、充実が図られました。小学校でも英語が必修となりました。さらに2025年以降の改訂に向けて議論されている項目としては、グローバル化・AI社会・気候変動などをどう取り上げるか、共生社会・持続可能性・情報リテラシーなどをどう扱うかなどが議論されているようです。
内容に関しては一つ一つ中身と実行方法を見ないと評価できませんが、それほど間違った方向に進んでいるようには見えません。戦前の思想統制教育の時代と違って、「何を教えるか」については目に余る的外れを心配する必要はないように思うのです。それよりも問題なのは「どう教えるか」つまり生徒の動機づけや教え方における教師の巧拙だったりします。今でも暴力指導が報道されるようではその指導力レベルの低さこそが心配です。授業時間にしても、子供たちの生活サイクルにストレスを与えないでしょうか?生きる力はいいけれども、テーマをどう設定させるのでしょうか?心の教育はいいのですが、どんな内容をどんな方法で教えるのでしょうか?一斉授業の中で、遅れている子をどのように補うのでしょうか?などなど、具体的に見てみないと判らないことがたくさんあるように思うのです。
それにしても、これ、もしかして、教師側に相当高いスキルや見識を要求していないですか?プログラミングできる教師ってどれくらいいたのでしょう?それを全国の教師に一律に求めるのが学習指導要領なのですが、どこまでの水準を求めているのでしょう?アクティブ・ラーニングが取り上げられていますが、それはどの教師も効果的に運用できるでしょうか?これらを毎日のルーティンでやるとなると、レクチャープランも膨大です。そもそも、教員数足りてます?外野でみているだけのしあですが、はらはら心配です。
しかし、それらをクリアしてもなお、それなりに問題はあります。結局大学受験で選別が実施されることに変わりありません。大学格差がなくなったわけでも受験戦争がなくなったわけでもないのです。学歴社会に変化が無い限り、事情は変わりません。となると、落ちこぼれ~校内暴力~いじめ~引きこもり~ニート~家庭内殺人~無差別殺人へと続く連鎖は依然として存在しているのではないでしょうか。よく考えると、これらは「何を教えるか」とはもともと関係ない事象だったことに気付きます。
これからの教育の可能性
さて、しあの自習室で、やっとこれまでの教育の経緯と現時点での問題点をまとめることができました。これらを材料に、これからの教育政策の方向性について、いくつかの可能性・選択肢をリストアップしておこうと思います。本当に私見ですので、本気で読まないでくださいね。ここまででも相当の文章量ですからね。これからも相当に多い文章ですからね。無理しないで下さい。
1.受験戦争の消滅
どうも、戦後教育が引き起こしたと考えていた大惨事の元凶は、教育が何をどう教えていたかということではなく、高度経済成長を実現するために構築された「学歴社会」が原因だったようです。優秀な人材を選別して育てるという資本主義原理を露骨に推し進めたことにより、そこに死屍累々たる負け組を生み出し、落ちこぼれ~校内暴力~いじめ~引きこもり~ニート~家庭内殺人~無差別殺人という連鎖を作り上げたのでした。それは資本主義の素直な欲求であり、それによって高度経済成長を実現し、国民の生活を前よりは豊かにしたのも事実です。それを良しとして後押ししたのはわたしたち国民でした。ただ、どんな犠牲の出かたをするかまでは、よく判っていなかったのだと思います。この構造が変わらない限り、負け組一党の反乱は続くでしょう。
では、この構造は絶対変わらないのでしょうか?しあはどうもそうとは限らないように感じています。まず、資本主義自体がどんどん減速しています。これは一時的傾向ではなく、それこそ構造的衰退に見えて仕方ありません。日本では失われた30年と呼ばれますが、アメリカや韓国も相当です。元気がよいように見えるトランプ大統領ですが、しあにはアメリカの余裕の無さが突き動かしているようにしかみえません。別記事でアメリカ経済の実態を調べてみようとも思います。韓国も相当に苦しいことが判っています。もう、暴動発生直前、というかあちこち起こってますよね。
もちろん、資本主義が簡単に死滅するとは思いません。それは「資本主義みたいなもの」として、時代環境に対応し変化しつつ生き延びるものだと思います。でも、これまでのように、「金にものを言わせて」強引に打って出ても、そう簡単に収益が上がらないようになっています。どんなものでも、商品が少ないうちは売れますが、世の中にモノが満ちてくるとだんだん売れなくなります。需要と供給の関係は嘘つきません。売れなくなったらまた別の商品もしくは別の地域に乗り換えればいいのですが、それがだんだん少なくなってくるのです。それにいくら良い商品でも、相手にそれを買う力が無ければ売れません。市民にそれを買う力がなければ内需は停滞するだろうし、相手の国から奪い取るばかりの貿易にはいつか限界がくるのです。自分さえよければいいというのが資本主義の基本ですが、それがだんだんできなくなります。ともあれ、資本主義も生き残るために修正をかけないといけない時がいつかやってきます。目先の利益に固執するのではなく、長い目で継続的に存続できる方法を模索するに違いありません。SDGsって、そんなニュアンスを持っています。もしかして、当面の企業の儲けを抑えてでも労働者の給与をあげ、継続的な内需を実現する構造を作ろうとするかもしれません。このあたりは経済学のお宿で詳しく取り上げようと思います。
もし、資本主義が路線を変更して、目先の利益中心主義から継続的安定収益を模索するようになった場合、状況は変わる可能性があります。そうなれば、勝ち組だけが高収入を得るのは不整合になります。負け組もきちんと収入があり、購買力を担う安定的存在としていてもらった方が、長期的収益計算がしやすくなります。まあ、一種の計画経済といえるかもしれませんね。そんな時代に求められる人材の資質としては「自分さえよければいい」なんて人は邪魔で、お互いを思いやり、バランスよく社会全体を考えられる人が求められるんじゃないかと思います。学歴的に負け組であったとしてもきちんと生活が補償されるようになれば(最近ベーシックインカムという言葉を聞きますよね)負の連鎖は断ち切ることができますし、基本補償があればそれによって個々人の生活に必要な学力を補うことも可能になるかもしれません。それだけではありません。ワーク・ライフバランスが徐々に改善されていけば、優秀な人も、もっと落ち着いて質の高い学力を得る機会を増やすことも可能かもしれません。まあ、そんな社会になればあちこち費用がかさみ、高給を取れる人があまりいなくなるとは思いますけどね。慣れないうちは大変かもしれません。
でも、モデルがないわけではありません。北欧の高福祉国家があるじゃないですか。高い税金で高福祉を実現していますが、かと言って一人当たりGDPも世界トップクラスです。もちろん、それなりに問題や課題を抱えているわけですが、そうした生き方もあるということです。高収入だけが幸福の全てではないでしょう。もちろん、収益第一主義から転換したことによって、グローバル経済の中で国内企業が敗北衰退する危険性もあるでしょうから、国家が防衛保護しながら国際競争力を維持するなど、今までにない国政の転換が必要なのは言うもでもありません。転換するとしたらフルセットで全体として変革しないとだめでしょうね。今の国会議員様を思うと・・・、当分無理かな。でも、例えばアメリカみたいに「大学に入ること自体は簡単で、ただし卒業が難しい」とかフランスみたいに「授業料無料」など、制度変更することくらいはできそうなものです。そうすれば、受験競争とか受験地獄とかいう惨状は緩和できるのではないでしょうか。少子化もいきつくところまで来ているし、そろそろバッサリ変える政治家は出てこないでしょうか?
もしこんなふうに高学歴が高収入を意味する傾向を弱めていけば、受験競争や落ちこぼれを少なくしていく可能性があります。また、ベーシックインカムがあるのなら、自分なりの能力に見合った仕事で、自ら工夫して仕事をすることも人生の選択肢となる可能性が出てきます。もしそんな時代が来たら、そこで必要になるのは「自分で課題を見つけ、分析し、解決策を考えだし」「周囲との関係を大事にして協力して生きていく」能力になるのではないでしょうか。ここで、前項最後に「検討されている」として記した学習指導要領の内容と路線が近づいてきます。もしかして、しあがここで考えてるくらいのことは、文部省も考えているのかも・・・。
2.人間の自立
つまり、これまでの社会では、人は自立していませんでした。言いにくいことを言うと、人は資本主義経済の道具であり、操り人形として振り回されきただけだったみたいです。だから、生産やお金に関係ない知識や能力は評価されてきませんでした。例えば友達を思いやる能力とか、仲間と楽しく共同作業する能力の育成なんて、誰も取り上げてこなかったのです。そんな社会を黙認して生きてきたということの根底には、資本主義の経済支配から零れ落ちたら「生きていけない」という恐怖があったのではないでしょうか?もっとも、それは古来からの村落共同体でも同じで、共同体からはじき出されたら一人では生きていけないという事情はいっしょでした。生産を社会に依存して生きてきた人間は、社会の生産方式に逆らって生きることなど考えたくないのです。そこから外れることには「死」の恐怖が付きまといます。
でも、これを乗り越えて生きる人々が現れ始めました。例えばYouTuberです。伝統工芸士や大工さんや施工管理技士など技術職や介護士などもそうです。労働人口減少によって希少価値が上がりました。技術者として、一つの会社にこだわらなくても生活できるような立場の人々です。ミュージシャン、ダンサー、スポーツマン、写真家、料理研究家など、どんな職業でもYouTubeなどで自活する人が出てきました。飲食業でも、大手飲食企業に属さず、自分の好きな創造的料理で自営しようとする人が現れています。こうした傾向に、ベーシックインカムが導入されれば、自分のやりたい仕事にチャレンジしようとする人が増えるかもしれません。
人間の自立、例えば自営業を想定すると、そこに求められる能力も変わってきます。自営業ともなれば、関係する取引先や顧客とのコミュニケーション能力が問われます。自ら状況を調べ、問題をみつけ、目標を創り、達成方法を考え、意欲を持って実行していく能力が問われます。大企業の中にあっても、単純労働は機械化AI化が進むわけで、求められるのは創造的労働となります。ここでは上意に従って受動的に仕事をこなすのではなく、自らの考えで仕事を支配管理することが求められます。大谷翔平さんも、自分のやりたいことをやってるだけで、仕事をさせられている意識など持ち合わせていないと思いますが、そんな生き方を目指す人が増えてきているような気がします。
ここで必要になるのは「知識」ではありません。知識を使いこなす本当の「能力」になってきます。「能力」については別の記事で取り上げたいと思いますが、このように想定した社会生活に求められるのは、自ら働きかけて何かを作り出すレベルのものであることは言うまでもありません。人間関係についても、道徳の授業で「教えられた内容」を理解する程度では意味がなく、自らの「生き方」になっていることが求められると思います。自己肯定感とプライドに基づく社会規範の内面化が必要になると思うのですが、現在の学校でそれを促す授業ができるでしょうか?言いにくいのですが、最近ニュースで聞かれる教員の不祥事や落ちこぼれから始まる転落人生の果てに起きる無差別殺人事件の続発を見ていると、学校の先生にこのレベルを期待するのは間違っているような気がして仕方ありません。彼らに道徳の時間の効き目はなかったようです。
また、教育到達目標をそのような「自立した人間」のレベルに置いたとき、今の学習指導要領が示す指導内容が整合性のある水準にあるかどうかが不明です。サラッと見た限りではあちこち「?」マークが着いたのが現実です。どうやら「人間の自立」時代を生きる力を育てようとするなら、これからも継続的に精緻な研究が必要なような気がします。まあ、今回は教育史であって教育原論ではありませんので、詳しくは別のお宿で調べてみようと思います。
3.3世代家族の復活
田舎暮らしがちょっとブームになっているらしいです。そんな暮らし向きでいいなら、村落共同体での標準的家族構成である3世代家族の復活を目指してはどうでしょうか?
いろいろ論点はあるのですが、田舎で3世代で暮らすのなら、一人当たりの生活コストは都会の1/10くらいにはなります。子供が4人くらいいても、余裕で生活ができるでしょう。祖父母が孫の面倒を見れば、両親は安心して仕事に行けます。待機児童などという問題もありません。子供は村落共同体や大家族の中で人間関係の基本や人生観を学び、自然な人格形成を取り戻します。自営を基本とする人生を送るならば、学歴社会から派生する不幸の連鎖からは無縁となります。
しかし、ではなぜ戦後、人々は都会に流出していったのでしょうか?まず素朴に農村の収入不足があります。今でもそうかもしれません。長男は跡取りするにしても、次男以下は家族をもつ経済力を持ちえませんでした。だから「金の卵」と言われ都会に集団就職していったのです。資本主義の側からみても工場労働者が必要でした。農村を解体することで労働者をかき集めたのでした。都市部に団地を作り、そこに労働者を受け入れ、工場を稼働させたわけです。集団就職する側から見ても、因習渦巻く農村から自分の自由を獲得するための最短距離が都市部での就労でした。それはもう、希望に満ちた旅立ちであり、故郷を捨てる悲壮感はそれほどなかったと言います。
これまで、村落共同体の「いいところ」を描いてきましたが、経済状態に着目するとそれなりに悲惨な状態が続いていました。世界恐慌以降、戦時中となると、どこもかしこも惨憺たる生活。あげく敗戦。大黒柱を失った家庭もたくさんあったわけです。そうした農村地域では3世代家族が標準でしたが、そこでの暮らしぶりで有名なのが「嫁いびり」です。家長制であった戦前の社会通念から言っても、女性の地位は「ほぼ奴隷」と言って間違いなく、さらに「お嫁さん」となれば家族ヒエラルヒーの最下層でした。何か意見を言ったりすることは許されず、財布をもたされることもありません。義父母が不機嫌になれば、八つ当たりの対象が「お嫁さん」だったりします。それでも耐えるしかなかったのは、離縁して家を出て村落共同体から離脱すると、生きていくことが難しかったからです。戦前の農村地域の女性の中学就学率はほぼゼロでした。農家にそんな必要がなかったからです。それゆえ、街中で働く職能など持ち合わせていません。終戦を迎え、都市での就職口が出現したことは、旧態依然とした封建的家族制度の中で苦しんでいた人々にとっては、夢の人生への脱出口でした。
つまり、農村での3世代家族を否定する理由は、経済的困難と家族ヒエラルヒーによるストレスです。さらに一つ付け加えるとしたら、娯楽施設(ディズニーランド・東京ドーム・歌舞伎座)や趣味嗜好提供店舗(おしゃれ・宝石・ゲーム)が無いことでしょうか。未知のものに興味を示す性質があるヒトにとって、都会は夢の国だったりします。ヒトは幻想に浸りたい生き物です。大きくいうと、この3つの障害さえなければ、3世代での田舎暮らしは楽園かもしれません。
一つ目の経済ですが、農業以外に自営能力がある人なら、生活コストが低い分、だいぶ有利に生活が可能です。リモートワークをしている人の中に田舎暮らしを楽しんでいる人が増えています。ネットワーク環境さえ整っていれば、都市部で無理に高い家賃を払って暮らす必要がありません。また、人口減少で農業後継者も不足しており、意欲さえあれば農業収入だけでの家計成立も可能かもしれません。平均的年金生活者なら、貯蓄も可能でしょう。まったく問題ないとは言いませんが、経済面ではそれほど高い障害はないと思われます。むしろ、都会生活より有利?
2つめの家族内の人間関係、村落内の人間関係。家族関係については、家族そろって勉強会で解決しましょう。昔と違ってパワハラやいじめに対する原因分析や対策ははっきりしているわけです。カウンセラーを囲んで勉強会を開催し、親子関係や家族ルールを取り決めたら、ほぼ克服できるはずです。それができたら3世代家族暮らしを考えたらよいと思います。
3つ目の欲望解脱。こればかりは個々人の人生観です。ただ、人類は資本主義に踊らされて要らぬものを欲しがるように飼いならされてきました。ダイヤモンド?食べられませんよ。人間関係に階級構造をつくり上位に立ちたい、つまり承認欲求を満たしたいという心理が生み出した幻想欲求にすぎません。高級写真機?きれいな画像は撮れますが、高いカメラを買えば写真がうまくなるわけではありません。きれいなドレス?すぐにあきるでしょ。ごめんなさい。こうしたことは人それぞれの判断ですね。納得できないひとは自己責任で街に飛び出して自分の人生を歩んでください。人生の主人公は自分です。
でも、ほんとに考えようなのです。田舎暮らしでもネットワーク環境があれば大概の音楽や絵画、動画、ニュース情報、言論情報は手に入ります。SNSに参画して意見を発することもできます。将棋や囲碁もネットで対戦できます。もちろんできないこともあります。サッカーなどのスポーツは無理かも。自分がどんな人生を歩みたいかをよく考え、それと適合するか考えて決めるとよいと思います。そんなこんなで、3世帯家族が増えてくると、資本主義にあおられた受験地獄に近寄らない人生選択も生まれてくるような気がします。経済困窮による非婚・少子化も解消されるのではないでしょうか?日本の景気が悪いと言いますが、悪くても豊かに暮らせる家族形態に避難して、それから立て直すのはどうでしょうか?
こんな家族が増えるとしたら、教育に求められる内容もまた変わってくるかもしれません。人生の意味を問い直し、ただただ資本主義的価値観に踊らされて生きるのではなく、様々な価値観と選択肢があることに気付かせるような教育はできないものでしょうか?
4.まとめ
いろいろ空想をしてみましたが、しあの心の底には一つの疑問があるのです。日本は高度経済成長をとげ、新しい技術や便利な道具が生まれて、社会は発達したはずなのです。なのになんで生活はこんなに苦しいのでしょう?なんで少子化が進んでいるのでしょう?なんで犯罪が増加してるのでしょう?株価をみれば、数字上の経済は発展してるらしい。でも、明日の生活を心配して暮らす人々が多数を占め、子供の貧困まで指摘される。
だから思うのです。頑張るだけ無駄じゃないですか?社会って、もしかして退化してません?資本主義は空回りしてないですか?そろそろ見切りをつけて、違う生き方もいろいろ考えるべき時代に差し掛かっていませんか?と。
それを考えるには、様々な時代、様々な地域で、どんな国がありどんな政治があり、どんな生活があるのかを知って、視野を広げてみる必要がありそうです。今の日本だけが人類社会の全てなわけではありません。とかく自分で自分を変えるのは難しいものです。自分が抱えている事情は変え難いものだと思い込んだりしています。自分の将来を考えようとするとき、他の国や歴史に視野を広げることも重要な気がします。これもいつか別のお宿でまとめてみたいと思います。
今回はここまで。またいつかお会いしましょう。