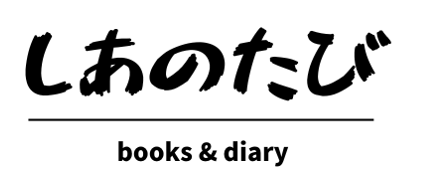前回は、最近の世界情勢や国会の動きなどを記録用にかいつまんで書き記しておきましたが、今回は、議論そのものが有効に機能するための条件を整理しておきたいと思います。これ知らないと、大概の議論はカラ回りの刑に処されてしまいます。今回は、「会議の進め方」から主要なコツを拾い集めてみました。
議論が成り立たない原因
議論の前提条件として「信頼関係がなければ、議論やコミュニケーションは成立しない」というお話は前にも取り上げましたが、加えるところ「議論」本体が「意味あるもの」として成立するためにもいくつかの条件があるようです。見てると、意図的に議論を壊したいわけじゃなさそうなんですけど、「会議がカラ回りしてるな~~」と思うことありませんか?原因としては、
- 最初からあまり関心が無い
- 自分の考えを曲げるつもりが無い
- 議論に必要な知識や思考力をもっていない
などでしょうか。しかも、意味のない議論をしてしまうと無用な対立を生んだりしますので、準備もなしに議論を始めるのは少し考えた方がよいかもしれません。メンバーが集まるだけで、時間とコストと機会損失が人数分かかるのですから。
1.最初からあまり関心が無い
1.については、養老先生の「バカの壁」にも指摘がありましたが、口先だけやり取りしているように見えて、実は内心そこに関心がない人がいる場合のカラ回りです。議論の必要性を感じてない人と話していても、意味ないです。会議をしようと思うなら、議論の前に「何を議論すべきか」というテーマの整理と問題意識の共有化が大切です。
この事前の調整と会議進行の企画を行うのが、「会議の主催者(例えば営業会議なら営業部長など)」と当日実際に会議進行をする「司会者」の仕事です。司会者といっても、その会議の目的を無視して勝手に進行していいわけがありません。その会議を主催する人との事前のすり合わせも大切です。会議の前には、何を問題としているのかを示す会議資料の事前配布が大切でしょう。そして実際に会議が始まったら、参加者が発言しやすい雰囲気をつくるための「アイスブレーキング」をしたあと、会議の目的つまり何を問題として話し合うのかを宣言し、参加者の問題意識を喚起するプロセスが欠かせません。普通は「基調報告」などで、現状にどんな問題があるのか、事実データや統計をもとにその重要性を示します。
ついでに、議事進行中の最重要ポイントを付け加えておきましょう。それは、「会議参加メンバーの発言を引き出すこと」です。なぜでしょうか?
そもそも問題の提示と対策を上意下達で指示するだけなら、会議は不要だからです。命令文書をメールすれば済むことです。会議をする最大の意義は、参加者の問題意識を共有化するとともに、多くの声を集めることで対策を豊かにするだけでなく、参加者個々が自ら考え工夫することで当事者意識をもち、主体的に問題解決に参画するのを促すことです。
想像してみてください。メンバーみんなが問題だと思っていることに一緒に取り組んでいるという「仲間意識・一体感」、そこに自分なりの工夫や提言で参画することで感じる「自分も役立っている」感、全体と自分の役割を理解することで生まれる「責任感」、誰から言われるでもなく「自分が自ら仕事に臨んでいる」という「当事者意識」。うまくいった会議からは、貴重なオマケがたくさんついてきます。これで結果が出たら、強い自信と自己肯定感、自己効用感、次の問題解決への意欲など、オイシイご褒美がたくさんまっています。これに対して、上意下達で命令され、指示されて仕方なくこなした場合、仕事の充実感にどれほどの差が出るでしょうか?というより、その組織の生産性はどれほどの違いになるでしょうか?
長くなりましたが、お話の出発点は「問題意識」をどう明確化し、共有化するかにあります。
追記:少しだけ余談です。人事考課制度によく「責任感」という評価項目がありますが、これはこうした組織全体と個々人の関係が明らかにされて初めて生まれるものです。個人が持って生まれてくるものではありません。なので、もし責任感がない社員がいたとしたら、それは社員個人の問題だけではなく、こうした会議などをうまく運営できていない組織管理者に問題がないかも考えるべきでしょう。何も手を打っていないのに、社員が勝手に責任感や帰属意識を持つと考える方がどうかしています。余談でした。
2.自分の考えを曲げるつもりがない
2.の自分の考えを曲げるつもりが無い人とは、議論してはいけません。例えば、違う宗教(宗派が違う場合も含む)の信者に「どちらが本当の神さまなんですか?」と議論を始めても、それぞれの信じる神を絶対視し、どちらもゆずる気がありません。議論をしても、最初から結論が動くことがありません。議論は無駄というものです。何事によらず「自分は絶対に正しい」と思い込んでいる人との議論は無駄です。
また少し寄り道ですが、これに対して科学の考え方は基本が違います。科学の定義についてはカール・ポパーの「反証可能性」が有名です。科学に絶対はなく、常にその時代の最先端の研究があるだけです。そもそも人間は常に不完全で、間違うことが当たり前。その誤りを見直し、書き換えることが科学の仕事だといえます。検証チェックができて当たり前。批判を受け付ける余地のない理論は科学ではありません。だから、科学は時代とともに進歩してきました。
そんなこんなで、自分の意見を変える意思のない人は、どんどん変わりゆく環境への対応を放棄しているに等しく、大きなハンデを背負って生きていくことになるわけですが、それはそれでご本人の人生かもしれません。ただ、最近、「他人は他人」といっていられない場面が多くなりました。こうなると、「なぜ、この人は自分の意思を変えようとしないのだろう?」とさかのぼって考える必要が出てきます。
でも、このタイプの人への対策が無いわけではありません。一つには1.で触れた会議進行です。これは司会者たるファシリテーターが、建設的論理的に議事進行することで、上司などの属人的権限に左右されることなく、論理的に解決策を紡ぎ出すことで、納得せざるを得ない結論に誘導することが可能です。このような「理論における合意の場」を創出できれば、「自分の意見を曲げない」上司も、反論するには合理性の土俵で戦うしかなくなります。会議は一種独特な教育機能を持っているようにも思われます。こうしたマネジメントの工夫を「属人的管理から情報に基づく管理への転換」といい、ピーター・ドラッカーが「MBO=目標による管理」において詳しく述べていますので、興味ある方はググってみてくささい。
あ、誤解がないようにお話しますが、ドラッカーの「目標管理制度」って結構有名ですけど、管理者に実力がないところに制度だけもってきても全く機能しません。念のため。
3.議論に必要な知識や思考力をもっていない
実のところ、現実にはこれが一番の難所のような気がします。
もう、You Tubeあたりでは「バカを何人集めてきてもましな結論が出るはずないじゃないか」などとズバズバ言う人がいるので、暴走しあも負けない程度におそるおそる言います。これまでの経験では、ある程度の教育水準にある人が相手だとあまり苦労せず議論が成立するのですが、そうでない人と話すときは、最初から議論をあきらめて聞き役で終わらせることが少なくありませんでした。現状の問題を正しく分析し対策を立てるのに必要な知識レベルに相手を引き上げるなど、しあの仕事ではありませんし、それが上司や社長、高齢の理事長だった日にはもう最初から放棄するしかありません。それに絶望して退職していった有能な先輩もたくさん記憶しています。
何かの漫画でみました。「無知とは罪」・・・無知なしあはショックを受けた記憶があります。そして、その罪は取り返しのつかない事件や大損害となって現れます。結局、組織が変わるのは、こうした事件が起こってからがほとんどではないでしょうか?どこかの先生が言いました。「ほっとけ。早くつぶれてくれた方が、新しいものが生まれる」・・・皮肉かもしれませんが、先生もたいがいヒドイかも。つぶれていくとき、巻き添えで職を無くす人のことを少しは気にかけてほしいものです。ともあれ、少し紹介するのが早いかもしれませんが、どうにも行き止まり感が強い最近の世の中を見ると、「加速主義」という言葉もキーワードとして記しておいたほうが良い気がします。ググってみてください。
さて、この3つ目の問題は、単純に言えば「教育」の問題です。関心のない人は、どんなに大事な話でも理解しません。まずこの第一関門から突破しないといけません。次に突破したい第二関門は、難しい話をどう解りやすくするかという課題です。専門家の先生がどんなに力説しても、言ってる意味がすんなり伝わるわけでもありません。社会は本当に複雑化高度化し、おまけにグローバル化や情報化が急加速しているのです。どの学問分野も急激に進歩した反面、その内容を理解するのは容易ではありません。しあも経験ありますが、専門の先生方が書いている「魔導書」の多くは、3行読むのに半年かかったりします。最高の入眠剤だったりします。でも、ここで道を選ばなければなりません。知らないまま茹で上がってもいいのか、それとも子供たちの未来のためにきちんと理解し、せめて助言くらいは残しておこうとするのか。
もっとも、専門家が集まってさえ、真実など誰にもわかってはいません。最先端と言っても、それは未来への途中でしかありません。英知を集めた議論で得た結論であっても、それは「その時その場限りでの合意事項」に過ぎません。なので、成田先生は言います。「議論にそれほどの価値はない」と。議論したから本当の結論が出るわけではないのです。むしろ大事なのは、「議論の根拠となっている知識が何なのか、また、そうした知識をどう取り扱っているのか」を理解することだと言います。たしかに、考える材料=「知識」がなければ考えること自体ができません。知識があっても「考える方法」を知らなければ、的確に問題を分析したり対策を考えることができません。未知の問題などこれからいくらでも現れるでしょう。成田先生が指摘するのは、こうした「考える力」自体を身につけておかないと、そうした未知の問題への対処ができないでしょ?ということなのだと思いました。(先生、解釈間違ってたらご指導ください)
この後、You Tubeでの展開では、専門家の難しい発言に対して「先生よくわかんないんですけど、それどういう意味ですか?」などと、一般人の代わりに疑問をなげかけ、解りやすい説明を引き出す「橋渡し役=ミドルマン」の存在が有効ではないかという提言がありました。また、宮台先生は、「社会一般論を話していても空回りするだけ。集落くらいの顔が見える集団でないと民主制は機能しない。そうした、現実生活に即した話し合いの中から生まれる絆、そうした場を創り運営できる人材を育てることが重要。日本全国の消防団や町内会など、拠点となりえる組織に出前講座を展開し続けたい。」とお話しされていました。ただし、以上はしあの抜粋ですので、勘違いしてるところもあると思います。正確に確かめたい人は、You Tubeを直接ご覧ください。
しあの感想
専門家の先生が何を考えているかを判るまでがそもそも大変なんですよね。でも、それが判らないと、対策提言が有効なのか判断できませんし、実際に対策を実行しようとしたとき、意図にそって正しく運用できません。本当に、「橋渡し役」をたくさん育ててほしいところです。
とりあえず、「意味のある議論が成り立つためには、参加メンバーの教養がものを言う。」というのだけはズシンときました。コミュニケーションの大部分は受け手側がどんなクオリティであるかに大きく左右されるのだそうです。さて、だとしたら次の課題は、「教育」ということになります。これはまた大きなテーマになるので、別のお宿で考えたいと思います。ではまたどこかの「本線」でお会いしましょう。